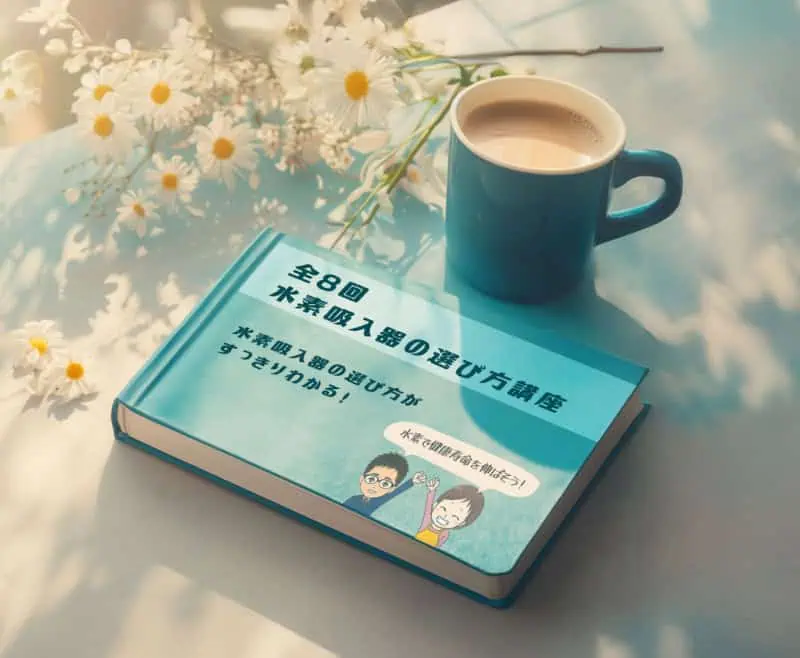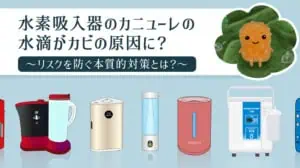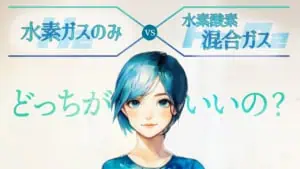水素吸入器を検討していると、スペック表に「PEM式」などの表記をみかけることがあります。

PEM式ってなんだろう?
と思っても、それが何を意味するのかよくわからないまま、なんとなくスルーしてしまっている方も多いのではないでしょうか。
実は水素吸入器には「PEM式」を含めいくつかの「水素生成方式」があり、
この生成方式の違いによって、
- 水素の純度
- メンテナンス性
- 安全性
- 装置の使いやすさや寿命
など、意外と大きな違いが出てきます。
今回は、家庭用・医療用水素吸入器でも使われている以下の4つの代表的な水素生成方式について、それぞれのしくみと特徴についてご紹介してみたいと思います。
- シンプルな電極式
- アルカリ水電解
- PEM式(PEM型水電解)
- 化学反応式
(完全には確認できていませんが、❶は水素吸入器では使われていないかもしれません)
 管理人KON
管理人KON水素吸入器を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
水素を取り出す仕組み|ヒントは理科の実験にあり
水素をつくる方法・・と聞くと、なんだかむずかしそうに感じるかもしれません。
でも実際には、中学校の理科でおこなった実験:
「水に電気を流して、水素と酸素を取り出す実験」
(=水の電気分解によって水素を取り出す)
【水 H2O + 電気 →水素 H2 + 酸素 O2】
この実験が、水素生成の基本的なしくみになっています。
 YUIさん
YUIさんそういえばそんな実験あったっけ・・
今回ご紹介する4つの水素生成方式:
- シンプルな電極式
- アルカリ水電解
- PEM式(PEM型水電解)
- 化学反応式
この4つについても、そのうち①〜③は電気分解式(電解式)ですね。
「① シンプルな電極式」と「② アルカリ水電解」は理科の実験に比較的近い方式で、それをさらに進化させたのが「③ PEM式」といえるかもしれません。
残る「④ 化学反応式」は、電気を使わない少しユニークな方式になります。
純粋な水は電気を通さない
電気分解についてひとつ押さえておきたいのは、「純粋な水は電気を通さない」ということです。
そのため、中学理科の実験では「水酸化ナトリウム」などを水に混ぜることで電気を流れやすくしていました。
この性質は、それぞれの水素生成方式の仕組みやリスクについて理解するときに役立つので、よかったら頭の隅にいれておいてください。
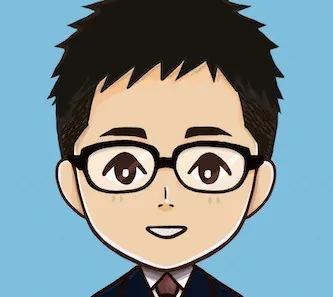 管理人KON
管理人KONそれではまずわかりやすいところ:「❶シンプルな電極式」と「❷アルカリ水電解」からそれぞれ見ていきましょう。
❶ シンプルな電極式
「シンプルな電極式」は、水の中に電極を入れ、電気を流すだけで水素を発生させる方式です。
 YUIさん
YUIさんすごくシンプルね。
具体的な製品の例
具体的な製品の例として、水素吸入ではありませんが、私も使っている水素風呂用水素生成器「リタライフ」はこのタイプです。


▲浴槽に電極を入れ、そこから水素が発生します。
精製水では電気が流れにくい→「純水ではない水」が必要
このシンプルなタイプには、「精製水」は使えません。
なぜなら先ほども触れたとおり「純粋な水は電気を流さない」からです。
電気が流れないということは電気分解も進まず、水素も発生しにくくなります。
そのため、このタイプの水素吸入器では、ミネラルウォーターや水道水など、「不純物(電解質となる水以外の物質)」をある程度含む水を使うことで電気分解を成立させることになります。
 管理人KON
管理人KON理科の実験での「水酸化ナトリウム」の役割をする「水以外の物質(不純物)」が必要なんですね。
リタライフも、お風呂のお湯は水道水(純水ではない)なので、水素が発生します。
水素は出るけど、リスクもある?
ただし、ここで気をつけたいのが水素以外の物質も発生する可能性があるということ。
たとえば…
- 電極に使用されている金属が不明で、溶け出すリスク(電極の素材による)
- 水に含まれる「水以外の成分」から、電気分解のプロセスで副産物が発生する可能性
このような可能性があります。
そのため、水素吸入器で(もしも)この方式が使われていた場合は注意が必要です。
❷ アルカリ水電解
この方式は、「シンプルな電極式」と同じく、
「水を電気分解し、水素を取り出す」
という方式ですが、より洗練された方式といえます。
電解質として「アルカリ溶液」を使用
先ほどの「シンプルな電極式」では、天然の水や水道水に含まれる「不純物」を電解質としていましたが、この方式では水酸化カリウムなどの「アルカリ溶液」を添加して電解質として使用します。
中学理科の実験における「水酸化ナトリウム」の役割をもつものを加えるわけですね。
具体的な製品例
アルカリ水電解タイプの代表的な水素吸入器としては、がん治療で成果をあげている『くまもと免疫統合医療クリニック』などで使われてきた、ヘリックスジャパン社の「ハイセルベーターET-100」(現在は廃番)などが挙げられます。


メンテナンス性はあまりよくない?
アルカリ水電解方式では、電気分解をすすめるための電解質として『水酸化カリウム(KOH)などの強アルカリ溶液』を使用します。
この強アルカリ溶液の取り扱いには注意が必要で、たとえば目に入ったり皮膚に触れたりすると、強い刺激ややけどのリスクがあるため、一般ユーザーが直接扱うことは推奨されていません。
そのため、メーカー側で一定時間ごとにメンテナンスする仕組みになっているケースが多いです。
たとえば「ハイセルベーターET-100」の場合
たとえば、ヘリックスジャパン社のハイセルベーターET-100では、
- 900時間の使用でアラームが表示され、メーカーでのメンテナンス時期を知らせる
- 1000時間で運転が停止
という設計になっていました。
 管理人KON
管理人KONこのようにユーザーがアルカリ溶液に直接触れるリスクを避けるために、一定の運転時間でメンテナンスが求められる仕組みがとられているんですね。
PEM式と比べると…
このあと説明する「PEM式電気分解」では、電解液を使わず精製水だけで水素を生成できるので、このようなアルカリ溶液の交換や安全対策は必要ありません。
メンテナンスの手間や安全性を考えると、PEM式のほうが使いやすいということは言えると思います。
では次に、PEM式とはどんな方式なのかについて見ていきましょう。
❸ PEM式(PEM型水分解)|精製水から水素が生成できる
ここまでご紹介した「シンプルな電極式」や「アルカリ水電解式」では、水に電気を通すために電解質(電気を通す物質)が必要でした。
PEM式はそこが違っており、不純物をふくまない『精製水』だけで水素が生成できる方式です。
電気が通らない精製水なのに、なぜ水素が出るの?
電解質(電気を通すための物質)がないと、水に電気は通りません。
ではなぜ精製水の電気分解で水素ができるのでしょう?
そのカギを握っているのが、PEM式の名前にもなっている「PEM(プロトン交換膜)」。
これは、水の中から水素イオン(H⁺)だけを選んで通す特殊な膜で、ここに電気と触媒(電極にコーティングされた金属)が加わることで、効率よく水が分解されるんですね。
 管理人KON
管理人KON詳しいメカニズムは少し難しくなるので、ここでは割愛します。
PEM式の特長
PEM式には他の方式にはない、以下のような様々なメリットがあります。
- 精製水だけで水素が作れる(電解質は不要)
- 発生する水素の純度が高い
- アルカリ液などの危険物を使わないので安全性が高い
- 消耗部品が少なく、メンテナンスも比較的ラク
- 装置をコンパクトにできる
このようなメリットがあるため、現在では多くの水素吸入器メーカーがPEM式を採用するようになっているんですね。
 管理人KON
管理人KONたとえば、先ほど触れたヘリックスジャパン社の「ハイセルベーター」シリーズも、これまでの機種はアルカリ水電解式でしたが、最新機種ではPEM式を採用しています。
現在の主流はPEM式
以上のような特徴により、現在の家庭用の水素吸入器ではこのPEM方式がもっとも広く使われており、これまで見てきた3つの電気分解式の中でも「もっとも標準的な方式」といえるかもしれません。
ちなみに電気分解式の水素吸入器について、
『電極の種類(チタンやステンレスなど)」によって水素吸入器の安全性に違いが出る』
という話を耳にすることがありますが、この話は電極の種類以前に、
「PEM式やアルカリ水電解など、電解方式によって、適した電極の種類が異なる」という事情が抜け落ちて語られることが多いので注意が必要です。
参考記事:ステンレスの電極は危険でチタン+プラチナじゃないとだめなの?医療用水素吸入器メーカーからの明快な回答

❹ 化学反応式|電気を使わずに水素を発生
これまでご紹介してきた方式はすべて、「電気の力で水を分解し、水素を発生させる」というものでした。
ですが、水素は「化学反応」によっても発生させることができます。
それが、ここでご紹介する「化学反応式」というタイプです。
化学反応式の特徴
以下に、化学反応式の主な特徴をまとめてみましょう。
①化学反応により熱を発生しつつ水素を生成する
アルミニウムと酸化カルシウムを主成分とする「水素発生剤」に水を加えると、化学反応によって水素が発生します。
このとき熱も同時に発生するため、やけどを防ぐためにも直接触れず、専用のかごなどに入れて使うのが一般的です。
②水素量は反応直後がピークで、その後は徐々に減少
化学反応式では、反応直後に水素発生量が最も多く、そこから時間とともに徐々に減っていきます。

安定的に一定量の水素を発生し続ける電気分解式とは決定的に異なる点ですね。
③ 毎回の使用にコストがかかる
化学反応式では、水素発生剤が使い切りのため、吸入のたびに「水素発生剤」のコストが必要になります。
④初期費用はリーズナブル
ある程度信頼のおける電気分解式の水素吸入器の場合、数十万円以上しますが、化学反応式のものは水素発生剤とのセットで数万円から購入でき、比較的始めやすいという特徴があります。
手軽に導入できる、面白い存在
以上のように、取り扱いやランニングコストには注意が必要ですが、気軽に導入しやすいのが化学反応式の大きなメリットといえます。
また電気が不要で水道水さえあれば使えるので、外出先や旅行先で使いやすく、「家では電気分解式、外出先では化学反応式」という使い分けをされているケースも多いようですね。
まとめ
以上、今回は「水素吸入器に使われている4つの水素生成方式」について、それぞれのしくみと特徴を見てきました。
同じ「水素吸入器」といっても、その中身──つまり水素をどうやって取り出しているか?という方式によって、使いやすさや安全性、メンテナンス性、さらにはランニングコストまで、意外なほどに違いがありますよね。
購入前にこれらの違いを知っておくことで、「自分の目的やライフスタイルに合った吸入器」を選びやすくなると思います。
水素吸入をこれから始めてみたいという方にとって、少しでも参考になればうれしいです。